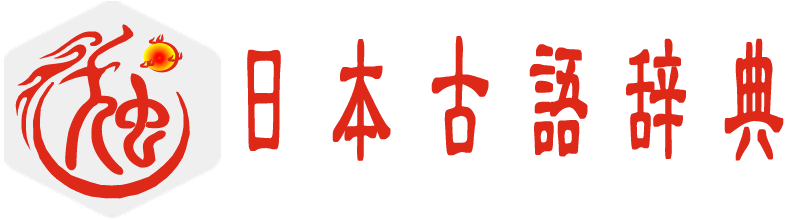かよ・ふ 【通ふ】 自動詞 ハ行四段活用活用{は/ひ/ふ/ふ/へ/へ} ①通う。出典伊勢物語 八三「昔、水無瀬(みなせ)にかよひ給(たま)ひし惟喬(これたか)の親王(みこ)、例の狩りしにおはします供に」[訳] 昔、水無瀬に通いなさった惟喬親王が、いつものように鷹(たか)狩りをしにおいでになるお供として。②通る。行き来する。出典新古今集 春下「風かよふ寝覚めの袖(そで)の花の香(か)に薫る枕(まくら)の春の夜の夢」[訳] ⇒かぜかよふ…。③(男が女の家へ)通う。結婚する。出典伊勢物語 一一〇「むかし、男、みそかにかよふ女ありけり」[訳] 昔、男がこっそり通う女がいたということだ。④通じる。出典万葉集 三九六九「思ほしき言(こと)もかよはず」[訳] 思っている言葉も通じない。⑤よく知っている。通じている。出典源氏物語 御法「仏の道にさへかよひ給(たま)ひける御心の程などを」[訳] 仏道にまで通じておられるお心のほどなどを。⑥似通う。通じる。出典奥の細道 象潟「江の縦横一里ばかり、おもかげ松島にかよひてまた異なり」[訳] 入り江の東西と南北はそれぞれ一里(=約四キロメートル)ほどで、ようすは松島に似通っているが、また違っている。⑦交差する。入り交じる。出典拾遺集 雑賀「松が枝(え)のかよへる枝をとぐらにて」[訳] 松の枝で交差している枝を鳥のねぐらとして。⑧つながっている。通じる。出典奥の細道 象潟「東に堤を築きて秋田にかよふ道はるかに」[訳] 東には堤を築いて、秋田に通じる道が遠く続いており。 参考③は王朝時代の貴族の結婚形態を反映している。女性の家に男性が通うという形であった。⇒古典の常識 |