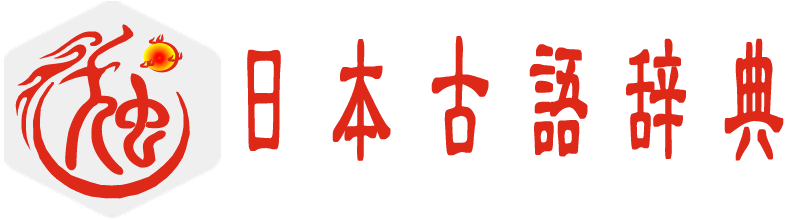もののふの… 分類和歌 「もののふの(=枕詞(まくらことば))八十(やそ)宇治川の網代木(あじろき)にいさよふ波の行く方知らずも」出典万葉集 二六四・柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)[訳] 宇治川に仕掛けてある網代の木にさえぎられて行きなずんでいる波が、これからどこへ行くのかわからないことだ。 鑑賞人麻呂が近江(おうみ)の国(滋賀県)から上京する際の歌。世の中の無常を詠んだ歌とする説もある。「もののふの八十」は氏(うじ)を導く序詞(じよことば)で、「氏」に「宇治」をかけた。「網代」は魚を捕るための仕掛けで、川の中に杭(くい)を打ち並べ、その端に簀(す)を設けたもの。「網代木」はその杭。「いさよふ」は、停滞するの意。 もののふの… 分類和歌「もののふの(=枕詞(まくらことば))八十少女(やそをとめ)らが汲(く)み紛(まが)ふ寺井の上の堅香子(かたかご)の花」出典万葉集 四一四三・大伴家持(おほとものやかもち)[訳] たくさんの少女たちが入り乱れて水を汲み合っている、寺の井戸のほとりに咲いているかたくりの花よ。 鑑賞可憐(かれん)なかたくりの花に少女たちを配して、うららかな山野の春を描いた歌。 もののふの… 分類和歌「武士の矢並(やなみ)つくろふ籠手(こて)の上に霰(あられ)たばしる那須(なす)の篠原(しのはら)」出典金槐集 冬・源実朝(みなもとのさねとも)[訳] 武士たちが、背に負っている箙(えびら)にさした矢の並びを直そうとして、背後にまわした籠手の上に霰がたたきつけ飛び散ることよ、ここ那須の篠原で。 鑑賞「霰」の題で詠まれた歌。武士の勇壮な狩猟の風景を表現した。「籠手」は左手をおおう防具。「たばしる」は、激しく飛び散るの意。「那須の篠原」は、下野(しもつけ)の国(栃木県)にある狩り場で、父の頼朝(よりとも)もこの地で狩猟を催したことがある。 もののふ-の 【武士の】 分類枕詞「もののふ」の「氏(うぢ)」の数が多いところから「八十(やそ)」「五十(い)」にかかり、それと同音を含む「矢」「岩(石)瀬」などにかかる。また、「氏(うぢ)」「宇治(うぢ)」にもかかる。出典万葉集 二六四「もののふの八十宇治川の網代木(あじろき)に」[訳] ⇒もののふのやそうぢがはの…。 |