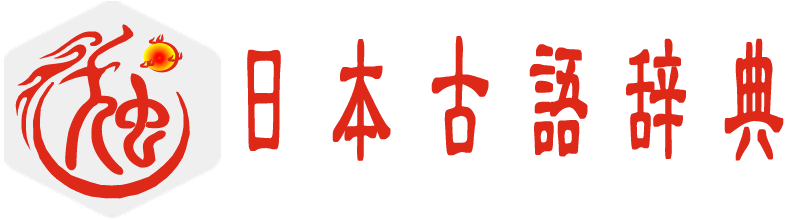お・ふ 【負ふ】 >[一]自動詞 ハ行四段活用活用{は/ひ/ふ/ふ/へ/へ} 似合う。ぴったり合う。ふさわしい。出典古今集 仮名序「文屋康秀(ふんやのやすひで)は、詞(ことば)はたくみにて、そのさま身におはず」[訳] 文屋康秀は、言葉(の使い方)は上手だが、その歌の姿は内容とぴったり合わない。 >[二]他動詞 ハ行四段活用活用{は/ひ/ふ/ふ/へ/へ}①背負う。出典伊勢物語 六「男、弓・胡簶(やなぐひ)をおひて戸口にをり」[訳] 男は、弓(を持ち)やなぐいを背負って戸口に(立って女を守って)いる。②こうむる。身に受ける。出典源氏物語 桐壺「朝夕の宮仕へにつけても、人の心をのみ動かし、恨みをおふ積もりにやありけむ」[訳] 朝晩のお勤めにつけても、他の女御(にようご)や更衣たちの心をひどく動揺させ、その恨みを身に受けることが積み重なった結果であったのだろうか。③借金をする。借りる。出典宇治拾遺 一・八「その人は、わが金(こがね)を千両おひたる人なり」[訳] その人は、私の金を千両借りている人である。④〔「名に負ふ」の形で〕(名として)持っている。出典古今集 羇旅・伊勢物語九「名にしおはばいざ言問(ことと)はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと」[訳] ⇒なにしおはばいざこととはむ…。 |