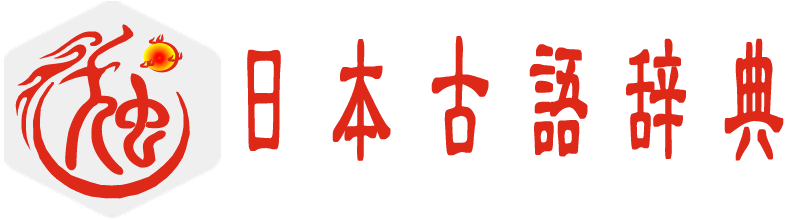
| 鲁虺日本古語辞典 | ||||
| 类目资源: 智虺堂 日本人文 康熙字典 汉语词典 毒鸡汤 谜语 名言 解梦 谚语 古籍溯源 异体字 大辞海 制度 语言翻译 | ||||
| 鲁虺日本古語辞典 / べし | 上一个 查看全部 下一个 |
べし | |
| ①〔推量〕…にちがいない。きっと…だろう。(当然)…しそうだ。▽確信をもって推量する意を表す。出典徒然草 一「人は、形・有り様のすぐれたらんこそ、あらまほしかるべけれ」[訳] 人間は容貌(ようぼう)や風采(ふうさい)がすぐれていることこそ、望ましいだろう。②〔意志〕(必ず)…しよう。…するつもりだ。…してやろう。▽強い意志を表す。出典竹取物語 御門の求婚「『宮仕へに出(い)だし立てば死ぬべし』と申す」[訳] (かぐや姫は)「(私を)宮仕えに出すならば、死んでしまうつもりだ」と申し上げる。③〔可能〕…できる。…できそうだ。…できるはずだ。出典大鏡 道長上「わが子どもの、影だに踏むべくもあらぬこそ、口惜しけれ」[訳] 私(=兼家)の子息たちが、(四条大納言の)影さえ踏むこともできそうにないのは、残念なことだ。④〔適当・勧誘〕…(する)のがよい。…(する)のが適当である。…(する)のがふさわしい。▽そうするのがいちばんよいという意を表す。出典徒然草 五五「家の造りやうは、夏をむねとすべし」[訳] 家の造り方は、夏(に暮らしやすいこと)を主とするのがよい。⑤〔当然・義務・予定〕…するはずだ。当然…すべきだ。…しなければならない。…することになっている。▽必然的にそうでなければならないという意を表す。出典竹取物語 かぐや姫の生ひ立ち「子となり給(たま)ふべき人なめり」[訳] (私の)子におなりになるはずの人であるようだ。⑥〔命令〕…せよ。出典平家物語 一一・先帝身投「西に向かはせ給(たま)ひて、御念仏さぶらふべし」[訳] 西(の方)にお向きになって、お念仏をお唱えなさいませ。 語法(1)「べし」の各音便形[ア] ウ音便・イ音便[イ] 撥(はつ)音便⇒べかなり・べかめり・べかんなり・べかんめり(2)命令の意味⑥は、主従関係がはっきりしている軍記物語の会話などに現れやすい。(3)未然形の「べく」 「べく+は」については、次の二とおりの説がある。[イ] の立場に立った場合にだけ、未然形が存在することになる。また、近世の「べくば」(「べくんば」)の「べく」は、未然形である。⇒は・ば | |