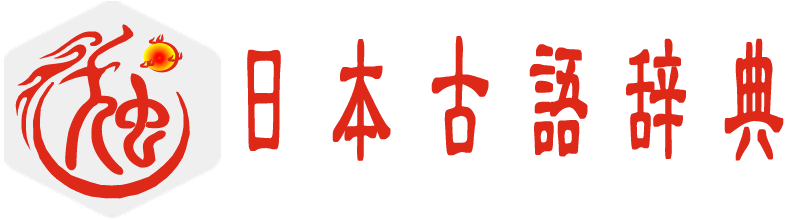らる 助動詞 下二段型《接続》上一段・上二段・下一段・下二段・カ変・サ変の各動詞型活用の語の未然形に付く。他の動詞型活用の語には「る」が付く。 ①〔受身〕…られる。出典枕草子 ありがたきもの「ありがたきもの。舅(しうと)にほめらるる婿」[訳] めったにないもの。(それは)舅にほめられる婿。②〔尊敬〕…なさる。お…になる。出典枕草子 うへにさぶらふ御猫は「『犬島へつかはせ。ただ今』と仰せらるれば」[訳] 「(翁丸(おきなまろ)を)犬島へ追放せよ。すぐさま」と(帝(みかど)が)お命じになるので。③〔自発〕自然と…される。…ないではいられない。出典徒然草 一九「なほ梅の匂(にほ)ひにぞ、いにしへの事も立ちかへり恋しう思ひ出(い)でらるる」[訳] やはり梅の香りによって、以前のことも(当時に)さかのぼって、自然となつかしく思い出される。④〔可能〕…することができる。…られる。▽中古には下に打消の語を伴って、「…できない」という意を表す。出典竹取物語 かぐや姫の昇天「あの国の人を、え戦はぬなり。弓矢して射られじ」[訳] あの国(月の世界)の人を、(相手に)戦うことはできないのだ。弓矢で射ることもできないだろう。 語法(1)尊敬の「らる」⇒る(2)可能の「らる」⇒る(3)「らる」は上代には例がなく、中古になってから発達した。(4)自発(③)・可能(④)の意の場合には命令形の用法はない。 参考「らる(る)」の意味を見分ける目安*「…られ給(たま)ふ」「…れ給ふ」の形で用いられる「る」「らる」は、受身か自発であり、尊敬ではない。表は一応の目安で例外もあるが、同じ意味の助動詞「る」にも当てはまる。⇒る |