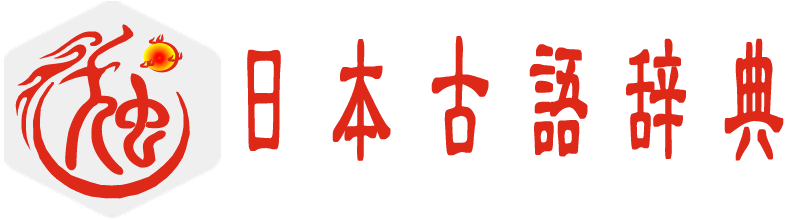へ 格助詞《接続》体言に付く。 ①〔方向〕…の方に。…に向かって。出典土佐日記 一二・二七「京へ帰るに女子(をんなご)のなきのみぞ悲しび恋ふる」[訳] 京の都に向かって帰るのだが、(この土佐で死んだ)娘がここにいないのだけが悲しく恋しく思われる。②〔帰着点〕…に。出典徒然草 五三「また仁和寺(にんなじ)へ帰りて、親しき者、老いたる母など枕上(まくらがみ)に寄りゐて」[訳] また仁和寺に帰って、親しい者や年取った母などが枕元に集まって座って。③〔対象〕…に対して。…に。出典宇治拾遺 一二・二二「この由を院へ申してこそは」[訳] このことを院に申し上げて(なんとかしよう)。 参考(1)語源は名詞「辺(へ)」(=「あたり」の意)と言われる。(2)「へ」と「に」の違い 「へ」は奈良時代には未発達で、「に」が一般的に用いられた。平安時代には、移動の方向や場所を示すときに「へ」を、その場所に行き着いているときには「に」を用いた。「へ」の②③の意味は中世に生じた。 へ 反復継続の助動詞「ふ」の已然形・命令形。 -へ 【辺】 接尾語…の辺り。…の方。「沖へ」「末へ」 へ 【辺・方】 名詞①辺り。ほとり。そば。出典万葉集 四〇九四「大君のへにこそ死なめ」[訳] (私は)天皇のそばでこそ死のう。②海辺。海岸。出典日本書紀 神代下「沖つ藻はへには寄れども」[訳] 沖の藻は海辺に近寄るけれども。[反対語] 沖(おき)。 へ 【上】 名詞〔「…のへ」の形で〕うえ。ほとり。出典万葉集 八七二「佐用比売(さよひめ)がこの山のへに領巾(ひれ)を振りけむ」[訳] 佐用姫がこの山の上で領巾(=肩にかけた白い薄布)を振ったのだろう。 へ 【家】 名詞家(いえ)。◆「いへ」の変化した語。 へ 【戸】 名詞戸籍上の家。また、それを数える語。 へ 【舳】 名詞(船の)へさき。船首。[反対語] 艫(とも)。 -へ 【重】 接尾語重なったものを数える語。「千(ち)へ」「八(や)へ垣」 へ 【経】 動詞「ふ」の未然形・連用形。 |